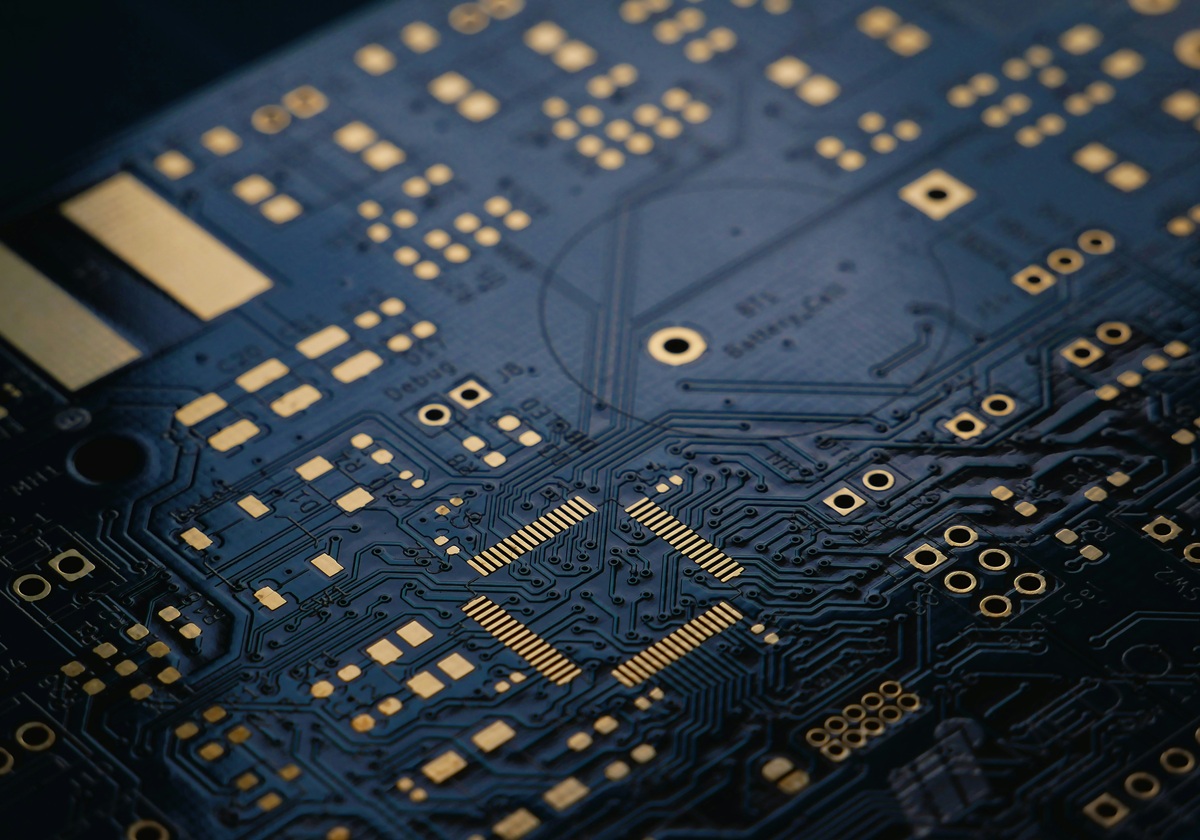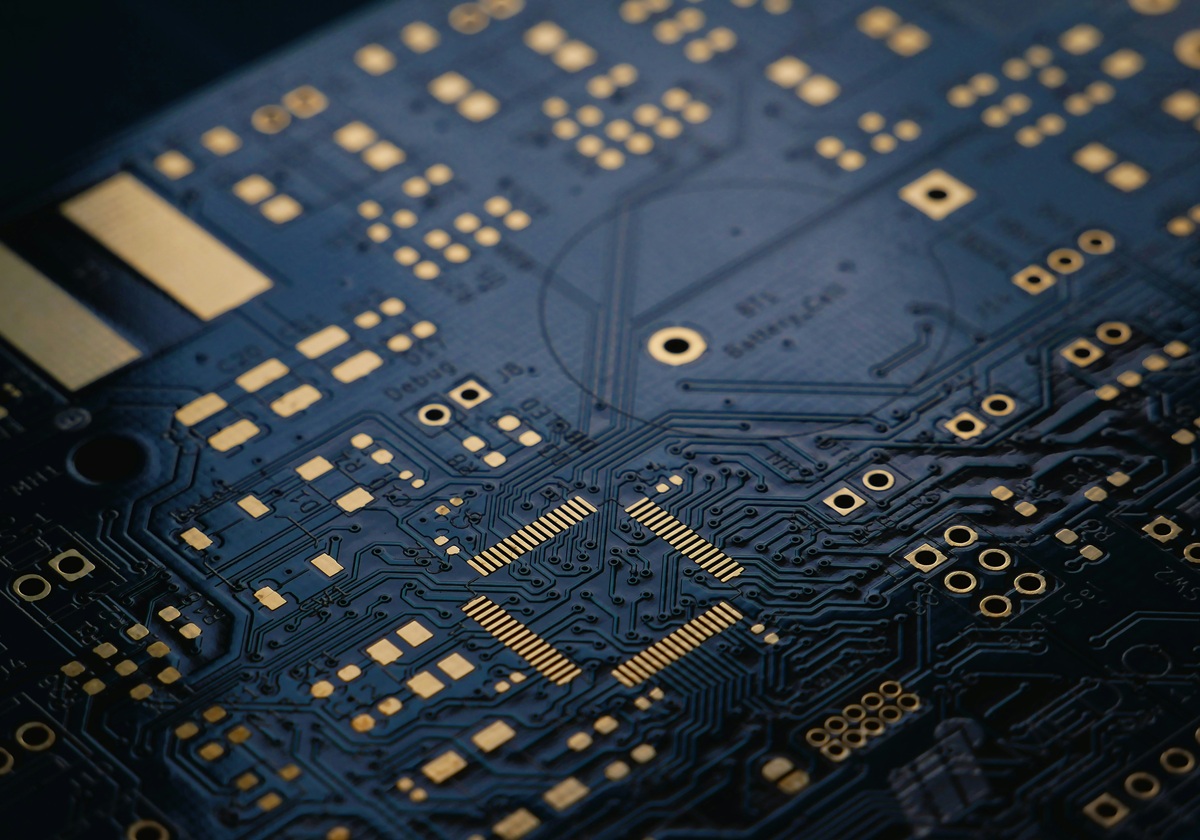 UnsplashのVishnu Mohananが撮影した写真
UnsplashのVishnu Mohananが撮影した写真
日本経済を支える柱の一つ――それが「半導体製造装置」である。2024年度の輸出金額は約5兆円規模に達し、自動車に次ぐ輸出産業として日本の貿易黒字を支えてきた。だが2025年、業界の勢力図に異変が生じつつある。
これまで絶対的な地位を誇ってきたのが東京エレクトロン(TEL)だ。塗布・現像装置で世界シェア約9割という圧倒的ポジションを築き、長年にわたって日本の半導体製造装置業界をリードしてきた。
しかし今、そのTELが業績予想を下方修正し、株価が急落している。主因は中国需要の急減と、主要顧客インテルの発注停滞だ。元半導体メーカー研究員で経済コンサルタントの岩井裕介氏に解説してもらった。
●目次
- 東京エレクトロンの「成長神話」崩れる
- 後工程の“日の丸”連合:ニコン・オーク製作所の台頭
- 業界構造の変化:「前工程」から「後工程」へ
- 東京エレクトロンの巻き返しはあるか
東京エレクトロンの「成長神話」崩れる
TELが発表した2025年3月期の営業利益予想は、前期比約20%減。これまで続いた好調な業績トレンドに陰りが見え始めた。背景には二つの構造的変化がある。
1.米中対立による輸出規制強化
アメリカの規制で先端半導体製造装置の対中輸出が制限されたことは、TELに直撃した。中国向け売上比率が3割近くを占めていたため、需要の急減は痛手となった。
2.インテルの業績不振と設備投資抑制
AI半導体需要を背景にNVIDIAやTSMCが設備投資を拡大する一方で、PC・サーバー分野で苦戦するインテルは投資を抑制。TELの主力取引先である同社の動きが、業績を押し下げた。
長期的には、TSMCが自社開発の塗布・現像技術を内製化する動きもあり、TELが誇った「前工程王国」の独占構造が少しずつ揺らいでいる。
対照的に、半導体後工程――すなわちテスト・パッケージング分野では日本勢がかつてない好調を見せている。
その象徴がアドバンテストだ。同社は半導体テスター(検査装置)の最大手であり、AIチップの性能確認に不可欠な存在だ。2025年3月期の営業利益予想を前期比3割増の3000億円に上方修正した。
AIサーバーや生成AI用GPUが爆発的に増産されるなか、テスト需要はかつてない勢いで伸びている。アドバンテストの株価も年初から5割以上上昇し、業界の主役交代を象徴する存在となった。
後工程の“日の丸”連合:ニコン・オーク製作所の台頭
もう一つ注目されているのが、露光工程の中でも「マスクレス露光」技術を巡る新勢力の台頭だ。
ニコンとオーク製作所は、解像度1μm級のマスクレス露光装置を開発。従来、露光工程ではフォトマスクを使って回路を転写していたが、この工程を省略できるため、コスト・時間の両面で革新をもたらす。
この技術は、AIチップや車載半導体など少量多品種製造に最適であり、台湾・韓国・欧州の後工程メーカーから受注が急増。
「前工程=東京エレクトロン」「後工程=アドバンテスト・ニコン・オーク製作所」という新たな構図が形成されつつある。
さらに業界の底力を支えるのが、ディスコとイビデンだ。
・ディスコ:半導体ウエハーを切断・研磨する装置で世界シェアNo.1。AI向け高性能チップの製造にはより薄く・精密な加工が求められ、同社装置の需要が急拡大。
・イビデン:半導体パッケージ基板を製造。NVIDIAやインテルの最新GPU基板を手掛け、後工程サプライチェーンの要として急成長している。
この両社の存在は、半導体装置業界の“縁の下の力持ち”として改めて脚光を浴びている。
業界構造の変化:「前工程」から「後工程」へ
半導体製造装置業界は、これまで前工程(露光・成膜・エッチング)を制する者が主導してきた。
しかし、AI半導体の時代に入り、「後工程」がより重要になってきた。理由は以下の3つだ。
1.AIチップの複雑化
1個のAIチップに数百億個のトランジスタが集積され、検査工程が飛躍的に増加。テスター・研磨装置など後工程の比重が上昇。
2.チップレット構造の普及
1枚のチップに全機能を詰めるのではなく、複数の小チップを組み合わせる“チップレット構造”が主流に。これによりパッケージング工程が極めて重要に。
3.生成AIブームによるGPU特需
GPUは演算密度が高く、歩留まりの確保にテスト工程が不可欠。AIブームが後工程を押し上げている。
実はこの“後工程シフト”は、日本企業にとって好機でもある。前工程では米アプライドマテリアルズ、蘭ASML、日TELという寡占構造ができあがっているが、後工程は依然として群雄割拠状態だ。そこに日本企業の技術が刺さる。
精密加工・高精度制御・クリーン環境制御といった分野は、日本の得意領域。ニコンのマスクレス露光、ディスコの研磨技術、アドバンテストのテスター精度は、いずれも世界トップクラスだ。
さらに、AIや自動運転向け半導体では「多品種・少量生産」が増えるため、日本式の柔軟な製造技術が生きる。
東京エレクトロンの巻き返しはあるか
もちろん、東京エレクトロンも手をこまねいているわけではない。同社は次世代EUV露光対応装置や、AIプロセス制御ソフトなどの開発を進めており、「後工程領域」への参入も模索している。
しかし課題は、事業構造の硬直性だ。TELの売上の約8割が前工程装置に依存しており、後工程への転換には時間を要する。
また、ASMLとの提携関係もあり、独自技術の自由度が制約されている側面もある。
市場では「TELが後工程を取り込めるか否かが、日本装置業界の競争力維持の鍵」との見方も出ている。
半導体製造装置は、単なる1業種ではない。自動車、家電、AI、エネルギー産業まで、日本の輸出と技術基盤を支える中核的産業である。
TELの失速は一時的な調整とも見られるが、産業構造の転換は不可逆的だ。アドバンテストやニコン、ディスコといった後工程メーカーが新たな成長軸となり、「日本半導体装置=前工程一強」から「多層構造」へと変化している。この変化を日本企業がチャンスに変えられるか――。
製造技術の裾野の広さと、AI時代に対応する柔軟な発想で、日本の真価が問われている。
(文=BUSINESS JOURNAL編集部、協力=岩井裕介/経済コンサルタント)