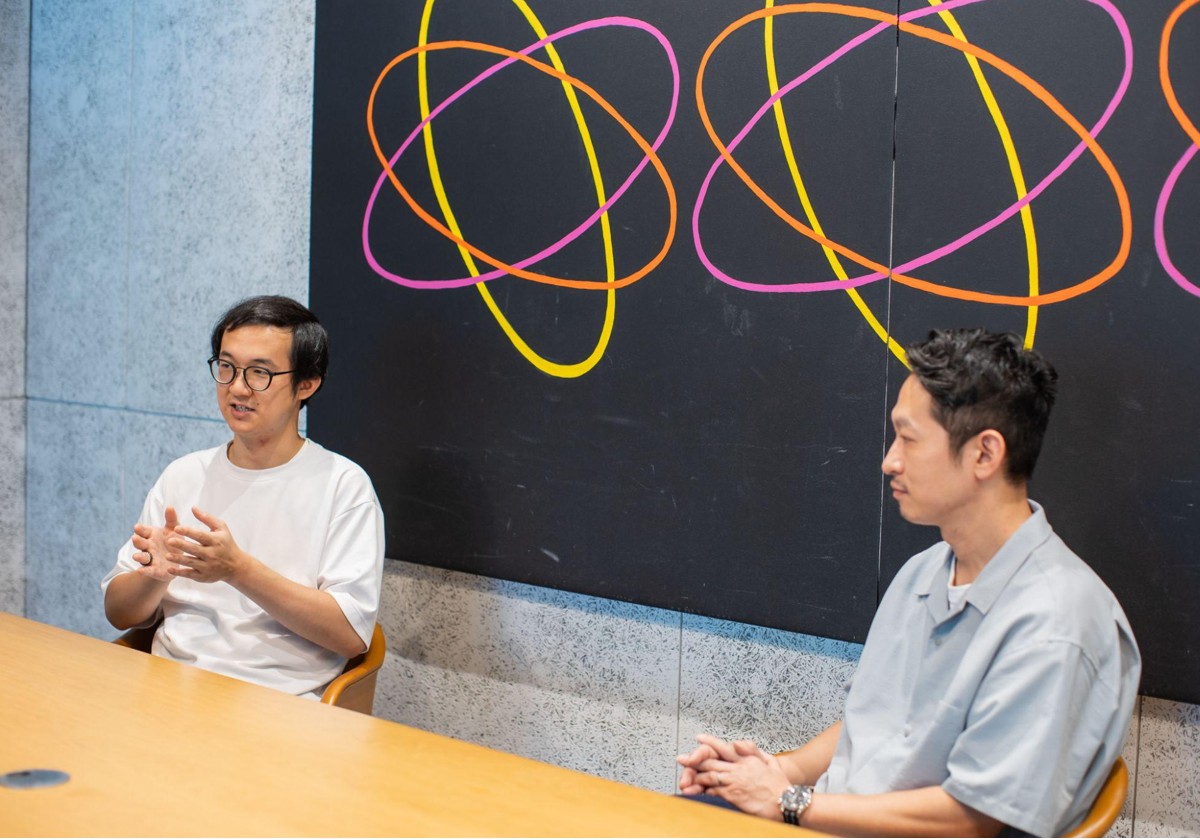
●この記事のポイント
・waypoint venture partnersは「街づくり」「産業成長」「個人のエンパワーメント」を軸に、レガシー産業へ挑むスタートアップに投資している。
・インフラや製造業には課題が山積する一方、DX導入の価値が認識されづらく、スタートアップ参入が難しい現実がある。
・Lenovoのサブスク型ハードウェア支援はスタートアップや中小企業の負担を軽減し、新たな選択肢を生み出す後押しをしている。
VCが投資する分野といえば、ITやディープテックなど先端技術を駆使した分野が真っ先に思い浮かぶかもしれません。
しかし、waypoint venture partners 株式会社が注目するのは、建設や製造といったレガシー産業や、インフラ産業などの既存領域です。
こうした領域に挑むスタートアップを、ハードウェア支援はどのように後押しできるのでしょうか?
今回は、waypoint venture partners 株式会社 代表取締役の平田拓己氏と、Lenovo Japanの中田竜太郎氏が、インフラやレガシー産業におけるスタートアップ支援の新たな可能性を、VCとハードウェア企業、双方の視点から語ります。
●目次
- 変わりゆく世の中と既存産業に新たな選択肢を
- インフラ・レガシー産業にスタートアップやデジタルが参入しづらい理由
- スタートアップにも既存企業にも有効なハードウェア支援
- 機能強化と選択肢の拡大、それぞれの方向から産業を変えていく
変わりゆく世の中と既存産業に新たな選択肢を

——waypoint venture partnersがどんなスタートアップ、企業に投資しているのか教えてください。
平田:waypoint venture partnersでは基本的にシード、プレシードステージを中心に投資をしている2023年に創業したVCです。
投資テーマはおもに、
・新しい街づくり
・産業の持続的成長
・個人のエンパワーメント
この3つを掲げています。
「新しい街づくり」は、人口が増えていくことを想定してつくられた、現在は老朽化が進むインフラを、実際には人口が減少していくなかでどう最適化していくのがよいのか?という部分を投資テーマにしたものです。
対象としては、電気やガス、水道だけではなく、医療や行政サービス、モビリティなども、広い意味でのインフラとして捉えています。
2つ目の「産業の持続的成長」のテーマも、背景にあるのは高齢化や人口減少です。担い手が減っていく一方、カーボンニュートラルなどの新たなトレンドはどんどん登場します。
このような状況のなか、とくにDX化がままならない、建設や不動産、製造、物流のようなレガシー産業を中心に何か新しいことができないか、新しいチャンスが生まれるのではないか、という観点で注目しています。
3つ目の「個人のエンパワーメント」は、教育や金融など、BtoCサービス(消費者向けサービス)のなかでも個人が生活していく上で最低限必要になる分野の選択肢をどう増やせるか、という部分を見ています。
かなり広い投資テーマを持ったVCではあるものの、共通しているのは、「世の中に対して新しい選択肢を生み出すことで、多くの中から人が最適なもの、自分に合ったものを選べるっていう状態をつくる」という考え方ですね。
——シードステージに投資することが多い、とのことですが、インフラやレガシー産業とスタートアップのつながりをあまりイメージできない方も多いように思います。インフラやレガシー産業に参入するスタートアップはどのような事業を行うことが多いのでしょうか?
平田:「直接参入型」と「間接支援型」の2つがあります。
直接参入型は、自分たちが製造業や建設業を行うというものです。商流や製造工程をゼロから立ち上げるイメージですね。
waypoint venture partnersの投資先にも自動車を製造している企業があるのですが、スタートアップだけあってつくるものがこれまでの自動車とまったく違います。
一方、間接支援型は、インフラやレガシー産業の企業を支援するツールやサービスを提供するものです。SaaS開発やロボティクスをイメージしてもらうのがわかりやすいですね。
元々、そういった業界にいた方が課題感を持って創業する、デジタル側の方が業界の課題を見つけて参入する、どちらのパターンもあります。後者の場合、業界構造を知るために一度インフラやレガシー産業に入り込んでみた、という面白いケースを耳にしたこともあります。
インフラ・レガシー産業にスタートアップやデジタルが参入しづらい理由

——産業における課題というお話がありましたが、インフラやレガシー産業ではどのような課題が存在しているのでしょうか?
平田:むしろ課題しか残っていない、という見方もできますね。
経理周りのデジタル化など、他業界ではすでに解消されたような課題も数多く残っています。請求書が紙ベースだったり、あらゆる連絡にいまだにFAXが使用されていたり、ということも多いです。業務連絡も、Slackなどのツールではなく個人コミュニケーションで使用されるLINEを使っているという話をよく聞きます。
このように多くの課題が置き去りになってしまう理由は、目の前の煩雑さや課題を解決することが、売り上げの増大やコストの大幅削減などの大きなインパクトにつながらないためでしょうね。
たとえば、建設業に従事する一人親方や現場の職人の方々からすると、バックオフィス業務がデジタル化されていなくても、最低限自分たちのやり取りができていれば受注はできるし売り上げも立つのです。
現場の方々からすると、あくまで施工や製造など現場での仕事が主体なので、新しい技術や知識を学ぶことが、目の前の仕事にまったくつながりません。
中田:それが、インフラやレガシー産業にスタートアップが入り込みづらい要因にもなっていますよね。
平田:そうですね。一見、スタートアップからすれば「チャンスだらけ」の業界に見えるのですが、いわゆる間接支援型などのスタートアップが考えうるSaaSなどのツールやサービスが、そもそも産業の根幹となる業務にマッチしない場合が多いのだと思います。
中田:こうした業界では、スタートアップが生み出すものに価値を感じてもらいづらい、ということなのかもしれませんね。
企業が生まれて存続していけるのは、生み出した価値に対して対価が支払われるからです。
課題ドリブンでスタートアップが生まれる場合、課題が明確に認識されている場合はそこに解決方法をぶつけやすいですし、ソリューションに価値を感じてもらいやすくなります。一方、課題が認識されづらい業界においては「対価を払うべきものではない」と思われてしまいます。
平田:本当に必要な場合はしっかりと対価を払って享受したい、という考えはあるのでしょうが、インフラやレガシー産業は「人が柔軟で最適化されている状態」なのですよね。ゆえに、DXのソリューションを入れたところで人が手を動かしているのとあまり変わらず、対価を払うほどのインパクトがない、という部分もあると感じます。
AIやロボティクスなども多く活用すれば効率化されると考えがちですが、建設業などは安全規制が厳しい上に作業の条件分岐が無限に存在します。現状、ロボティクスはそこまでの柔軟性を持つものではなく、AIも思考がブラックボックスなため、安全基準に正確に適合しているとは断言できません。
テクノロジーをすべて業務に適応させようとすると、人が手を動かすよりも開発費用のほうが高くなってしまうのです。
中田:まさにその通りで、建設業や製造業などでは、現時点で人が一番安い労働力であることが多いのですよね。
人を労働力としている以上、今後の労働人口の減少は大きな問題になるのですが、現在の経営層の方々が定年を迎えるまでの間には、その問題は大きく顕在化してきません。そうなると経営層にとっては、労働力不足に向けたDXなどにたった今お金を払うよりも、コストを削減し四半期の決算で利益を積み上げるほうが重要なことになります。
意思決定者のライフサイクルが、課題のライフサイクルを超えてしまっている状態なのです。
——しかし、この状態では対処しないまま課題が顕在化してしまいますよね。
平田:そうですね。今後、ノウハウを持っている方々がどんどん高齢化して業界から離れていきます。ノウハウが消えゆくなかで、このまま人の手だけで業務が回せるのか?という議論は必ず起こると考えています。
そうなると、デジタルに置き換えようという動きが加速したり、徐々にルールが変化したり、法的な後押しが出てきたりと、新たな選択肢を取れるチャンスや機会も生まれてくるのではないでしょうか。
スタートアップにも既存企業にも有効なハードウェア支援

——インフラやレガシー産業の課題、業界に参入する際のスタートアップの課題に対して、Lenovoのハードウェア支援「Lenovo for start-ups」が寄与できるポイントはどのようなものでしょうか?
中田:サブスクリプションでパソコンというデバイスを利用できるので、フィナンシャル面での負担を軽減できるところは大きなポイントだと感じます。
支払いを月々の定額にすることで、スタートアップという資金やリソースに限りある事業体においても、フィナンシャル面での不安なく、産業に対して高付加価値を生み出す可能性がある事業を維持できます。
平田:これはどの産業に参入しようとしているかにかかわらずいえることですね。現在、どの分野においてもパソコンは必須ですが、事業を加速させるという意味では最もお金をかけるポイントではないと思っています。
一気に数百万のキャッシュが出ていく購入という形を取らないことで、キャッシュフローを安定させる一助になりますよね。
また、利用するパソコンのスペックの相談ができるのは、インフラやレガシー産業に対して直接参入したいスタートアップにとっても有効です。
直接参入の場合、既存企業との差別化をしなければ、競争優位性は生まれません。当然、デジタルの仕組みが入る部分も多いですし、そういった仕組みをつくるパソコンにはある程度のスペックが必要です。
とはいえ、ただ高いものを使うのではオーバースペックになり、無駄な支出を生むことになります。
その部分を相談して、サブスクリプションでパソコンが利用できるという部分はLenovo for start-upsが持つ、インフラやレガシー産業のスタートアップに対する強みかもしれません。
逆に、想定よりも業務に対してパソコンが低スペックだった、という事態も防げます。
あとは、サポートが手厚いということがメリットですね。積極的なサポートが受けられずに、うまくデバイスやシステムが活用できないという例は多いです。
そういった意味では、スタートアップだけではなく、インフラやレガシー産業に存在する既存の中小企業にも有効な支援のようにも感じます。
中田:たしかに、インフラやレガシー産業は企業ごとにパソコンの導入率やOSのバージョンがバラバラで、パソコンを通じたコミュニケーションがシームレスにいかない場合があります。
たとえば、Zoomでミーティングを行う企業もあれば、パソコンのメモリ不足でZoomがうまく利用できない企業もあります。あまりにパソコンの導入状況やスペックに違いがあると、効率化に影響して取引が難しくなってしまうということにもなりかねません。
企業同士のコミュニケーションに制約がない状態をつくる、というのは非常に大切なことですね。
たった今必要なスペックを見極めて、バージョンサポートが終わったものに関しては新たなモデルに入れ替えることもサブスクリプションであれば可能です。
機能強化と選択肢の拡大、それぞれの方向から産業を変えていく

——それでは、最後にLenovoとwaypoint venture partners、それぞれがスタートアップ支援を通じてどのような社会を実現したいか、その展望を教えてください。
中田:スタートアップ向けにフレームワーク化された我々のサプスクリプションのモデルが、先ほど話に出てきたような中小企業のエンパワーメントにも寄与できればと思っています。
日本の企業は、9割以上が中小企業です。スタートアップはもちろん、既存企業の機能を高め、成長につながる支援として存在したいですね。
そのためには、どこでもユニバーサルに使えるパソコンというものに対して、その周辺機能を徹底的に強化していくことが非常に重要だと感じています。
平田:先に挙げたVCとしての3つのテーマにおいて、個人や企業に対して広く選択肢を提供できるようになればと考えています。
我々が投資するスタートアップが、対象とする顧客に新たな価値や選択肢を届け、さらに選んでもらえる存在になることに対して、微力ながらも後方支援を続けていきたいですね。
その先に、「あのタイミングであの企業が生まれてくれたからこそ、街のあり方や産業が変化した」と感じてもらえる状態が生まれればベストです。
*
インフラやレガシー産業とスタートアップ。一見、交わりのない二者にも思えますが、スタートアップは既存産業に新たな価値をもたらし、支えていく存在になりつつあります。
VCやハードウェア支援がその歩みを後押しすることで、日本を支え続ける既存産業にどのような変化が訪れ、どんな未来が描かれていくのか注目されます。
※本稿はPR記事です。